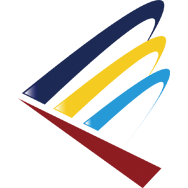八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続に関するご相談
2022年10月04日
母の相続手続きの際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(小倉)
小倉に一人で暮らしていた母が亡くなり、相続手続きを進めています。父は数年前に亡くなっているので、相続人は私と弟の二人になると思います。先日、手続きのために小倉にある銀行へ行った際、あらかじめ準備しておいた母が亡くなったことが分かる戸籍と自分と弟の現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは不十分だと言われてしまいました。ほかにどのような戸籍が必要で、どのように取得すればよいでしょうか?相続手続きが進められずに困っております。なお、母は亡き父と結婚するために長崎から出てきたと生前話していました。 (小倉)
相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
戸籍には複数の種類がありますので、混乱されることもあるかと思います。相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍が必要になります。
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。この戸籍により、お母様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。もしもお母様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。
戸籍を取得する際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。戸籍をたどるうちに、お母様の出身地である長崎の役所に戸籍を請求することも考えられます。直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。ただし、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。
たとえ、相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しいと思います。なかなか手続きが進まずに困っているという方は、八幡・中間相続遺言相談室の専門家による無料相談をご利用ください。小倉周辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にご相談ください。
中間の方より遺言書に関するご相談
2022年09月02日
将来のことを考えて遺言書を作成したい。行政書士が遺言書作成に強いと聞きました。(中間)
中間で生まれ育った70代の年金生活者です。最近「生前対策」という言葉を耳にすることが多くなり、その中で遺言書なら私にも気軽にできるのではないかと興味を持ちました。私には家族がいないので遺言書を作成する必要はないのかもしれませんが、独り身であるがゆえお金の使い道がなく贅沢をすることなくこの年までやってきた関係で微々たるもんですが蓄えがあります。自分の死後、身寄りのない私の財産がお国に取られるくらいならどこかに寄付してもいいかなと漠然とではありますが考えています。まずは遺言書について教えてください。(中間)
遺言書作成は行政書士にお任せ下さい。法的に間違いのない、ご相談者様に合った作成方法をご提案します。
相続では原則、遺言書の内容が優先されます。遺言書ではご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができますので、もしご相談者様がご自身の財産を寄付したいとお考えでしたら遺言書に寄付についてを記載することで実現します。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成しましょう。
では先に遺言書(普通方式)の3種類の方式についてご説明させていただきます。
①自筆証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで自筆して作成します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用も掛からず手軽ですが、法的に有効となる作成方法でないと無効となってしまいます。また、遺言者の没後は勝手に開封せず、家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。これは遺言書の書き換え等を防ぐため必ず守ります。なお、現在は自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになったため、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言 2人以上の証人を用意して公証役場に出向き、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。ご自身の財産を寄付される場合はこの方式で行います。なお、多少の費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで遺言書を作成します。作成した遺言書とともに公証役場に出向き、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式の不備などをチェックすることが出来ないため、無効となる危険性があります。現在はあまり使用されていません。
確実に寄付をしたいという場合は②の公正証書遺言を作成します。なお、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、寄付先がお決まりになりましたら、正式な団体名とともに寄付内容をご確認のうえ記載するようにしてください。
八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、中間エリアの皆様をはじめ、中間周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
八幡・中間相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、中間の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
小倉の方より相続に関するご相談
2022年08月03日
行政書士の先生に質問です。相続を進める上で遺産分割協議書は必要なのでしょうか?(小倉)
先日、小倉に住む父が亡くなりました。父は長いこと闘病が続いていたため、私たち家族もある程度は覚悟をしていたのもあり、葬儀の手配や諸手続きも今のところスムーズに進んでいます。父は遺言書を残しておりませんでしたが、私たちは法定相続人も把握しており、父の財産は小倉の実家と預貯金が数百万のみです。遺産分割協議も揉めることなく家族間で話がまとまりそうなのですが、このような場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(小倉)
相続は多額な財産を引き継ぐ手続きです。安心の為にも遺産分割協議書を作成しましょう。
相続では、遺言書がある場合には遺言書通りの内容で相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要がありませんので遺産分割協議書の作成も必要ありません。しかし、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い合意した内容を書き記した書面です。たとえ相続人間の仲が良く、遺産分割協議がスムーズに進んだとしても相続は多額の財産が手に入りますので、後々揉め事になるケースも少なくありません。後々相続人同士で揉めてしまった場合でも、遺産分割協議書があれば内容を確認することができますので安心です。尚、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きをする際に遺産分割協議書が必要となりますので、今後の相続手続きをスムーズに進める為に作成しておくことをお勧めいたします。以下遺産分割協議書が必要となる場面の例をご確認ください。
- 金融機関の預金口座が複数ある場合
(遺産分割協議書がない場合は、全ての金融機関の用紙に相続人全員の署名・押印が必要となります) - 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 相続トラブルの回避のため
上記のことを踏まえ、遺産分割協議がスムーズであっても遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。
相続は一生のうち何度も経験することではありませんので、何から手続きをすればよいか、必要な手続きは何か、ご存知ないのは当然のことです。相続手続きは複雑な手続きも多いため、知識がない状態で進めてしまうと後々トラブルにつながるケースも少なくありません。相続手続きでお困りの方は、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様の相続のお手伝いをさせていただいております。小倉で相続手続きに関するご相談なら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお立ち寄りください。