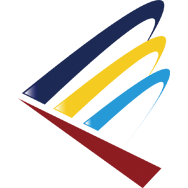八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2023年06月02日
相続手続きを行うことになったので、必要な戸籍について行政書士の先生教えてください。(宗像)
私の実家は宗像にあります。先月、実家に住む80代の父が亡くなったことをうけ、現在は相続手続きをしようと色々調べているところです。私には兄弟がいないため、相続人は私と母の2人になるかと思いますが、母は高齢なため、相続手続きはほとんど私がやっています。相続手続きには戸籍が必要とのことですが、戸籍について詳しくないため、必要な戸籍について教えていただけないでしょうか?また、併せて取得方法なども教えていただきたいです。(宗像)
相続手続きでは故人の出生から亡くなるまでの戸籍を収集する必要があります。
相続が開始されると相続人を確定するために戸籍を収集する必要がありますが、被相続人の出生から亡くなるまでに籍を置いた全市町村の戸籍を集めなければならないため、場合によっては非常に時間のかかる作業となります。なお、戸籍にはいくつか種類がありますが、相続手続きにおいては基本的に下記のような戸籍を集めます。
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の現在の戸籍謄本
戸籍には人の出生から死亡に至るまでのあらゆる情報「氏名、生年月日、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡等の身分関係等」が全て記録されていますので、被相続人の戸籍から、亡くなった時点で配偶者はいるか、他に子供がいないか等を確認します。養子や隠し子がいた場合は相続人が増えることになりますので早めに収集しましょう。
戸籍の請求は被相続人が今まで籍を置いた全地域で集めなければならず、被相続人が一生のうちに複数回転籍をしている場合はそれぞれを管轄する役所へ請求します。遠方に籍を置いたことがあり、直接役所に出向くことが難しい場合は郵送等での請求が可能ですのでまずは各役所のホームページなどでご確認ください。
戸籍謄本を揃えるには相当な時間や手間がかかります。他にも相続手続きには役所との手続きが多いことから思った以上に時間のかかる手続きが多くあります。手続きが進まずにお困りでいらっしゃる方は相続の専門家の手を借りることも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では宗像の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では宗像の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
小倉の方より遺産相続についてのご質問
2023年04月04日
法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(小倉)
小倉に住む50代女性です。先日小倉に長年暮らしていた父が亡くなり、今は家族で遺産相続について話し合いをしているのですが、遺産分割を進めるにあたり法定相続分の割合がわからず困っております。
私には妹がいたのですが、数年前に既に他界しております。妹には子どもが1人おりますので、相続人は母と私とこの子どもの3人になると思います。この場合、どのような割合で遺産分割すればよいですか?法定相続分の割合について教えていただきたいです。(小倉)
相続順位により法定相続分の割合が確認できます。
民法では遺産相続する人を「法定相続人」として定めております。そして被相続人の配偶者は必ず相続人であり、その他の相続人については民法で定められた相続順位によって法定相続分の割合が変わってきます。まずは法定相続人にあたるのが誰なのかを確認していきましょう。法定相続人とその順位は以下の通りです。
第一順位:子どもや孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
この順位の中で、上位にあたる人物が存在しない場合や亡くなっている場合は直下の順位の方が法定相続人となります。上位の人がご存命の場合は下位にあたる人は法定相続人とはなりません。
法定相続分の割合については、以下の通り民法で定められています。※以下民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のケースですと、法定相続分の割合はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子ども)が1/4、妹様は他界されていることから代襲相続が適用され、妹様のお子様が1/4となります。もし妹様にお子様が2人以上いらっしゃるのであれば、この1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。
なお、必ずしもこの法定相続分の割合に従って遺産分割しなければならないという訳ではありません。遺産分割協議にて相続人全員の合意が取れれば、自由な割合で分割して構いません。
今回はご相談内容に合わせて説明いたしましたが、ご状況によって法定相続分の割合が変わってくることもあります。ご自身での判断が困難だと感じるときは、遺産相続についての法律の知識をもつ専門家に相談されることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉や小倉周辺にお住まいの皆様の遺産相続手続きをサポートいたします。遺産相続においてご不明点がありましたら、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談までお問い合わせください。
小倉の方より遺言書についてのご相談
2023年03月09日
父と母が連名で署名した遺言書が見つかりました。この遺言書は有効なのか、行政書士の先生教えてください。(小倉)
小倉に在住の50代の男性です。先日父が長い闘病の末、小倉にある病院で亡くなりました。家族もある程度は覚悟しておりましたので、それほど慌てることもなく葬儀を終えることができました。
家族で協力して遺品を整理していたら、父の書斎で遺言書を見つけました。母に聞いたところ、どうやら生前父が元気なうちに相続について決めておこうと両親で相談して作成したそうです。私は5人兄弟の長男ですので、遺産分割の時に私に負担がかからないように配慮したのだと思います。
遺言書の内容は、父が所有していた金融資産や小倉にある不動産の分割方法のほか、母の財産にも及んでいるそうです。連名の遺言書は聞いたことがないのですが、この遺言書は有効になるのでしょうか。(小倉)
婚姻関係にあるご夫婦であっても、連名で署名された遺言書は無効となります。
民法では、「共同遺言の禁止」を定めております。
これにより2人以上の者が同一の遺言書を連名で作成することを禁じておりますので、残念ながら今回ご相談の遺言書は無効となります。
遺言書は遺言者の自由な意思を反映させ作成されるべきものです。もし複数名で遺言書を作成してしまうと、一人が主導権を握って作成してした可能性を否定しきれません。全ての人の意見が反映され作成されたかどうかを証明することが出来ないのです。
また、遺言者が遺言書を撤回する場合、連名で作成した全ての人の同意を得なければなりません。同意が得られない場合、遺言者は勝手に遺言書を撤回することが出来ず、遺言者の自由な意思を反映させるという遺言書の定義が崩れてしまいます。
遺言書の形式は法律で厳格に定められております。その形式に沿って作成されていなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまうのです。
遺言書は遺言者の最終意志を伝える大切な証書です。自筆証書遺言はご自身で作成し保管するので費用もかからず手軽ではありますが、法的に無効になる危険性もあります。遺言書には自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言もございます。公正証書遺言は公証人が作成し保管するため、遺言書が無効になる可能性は極めて低く、紛失や第三者による書き換えを防ぐことが出来ます。
もし今後、ご相談者様自身が遺言書を作成することがありましたら、相続手続きの専門家である八幡・中間相続遺言相談室へぜひご相談ください。遺言者の自由な意思を確実に残せるよう、全力でサポートいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉および小倉近郊にお住まいの皆様から相続に関する相談を多数いただいております。相続は人生に何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然のことです。八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談を無料で承っております。相続手続きに精通した専門家が親身になって対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。